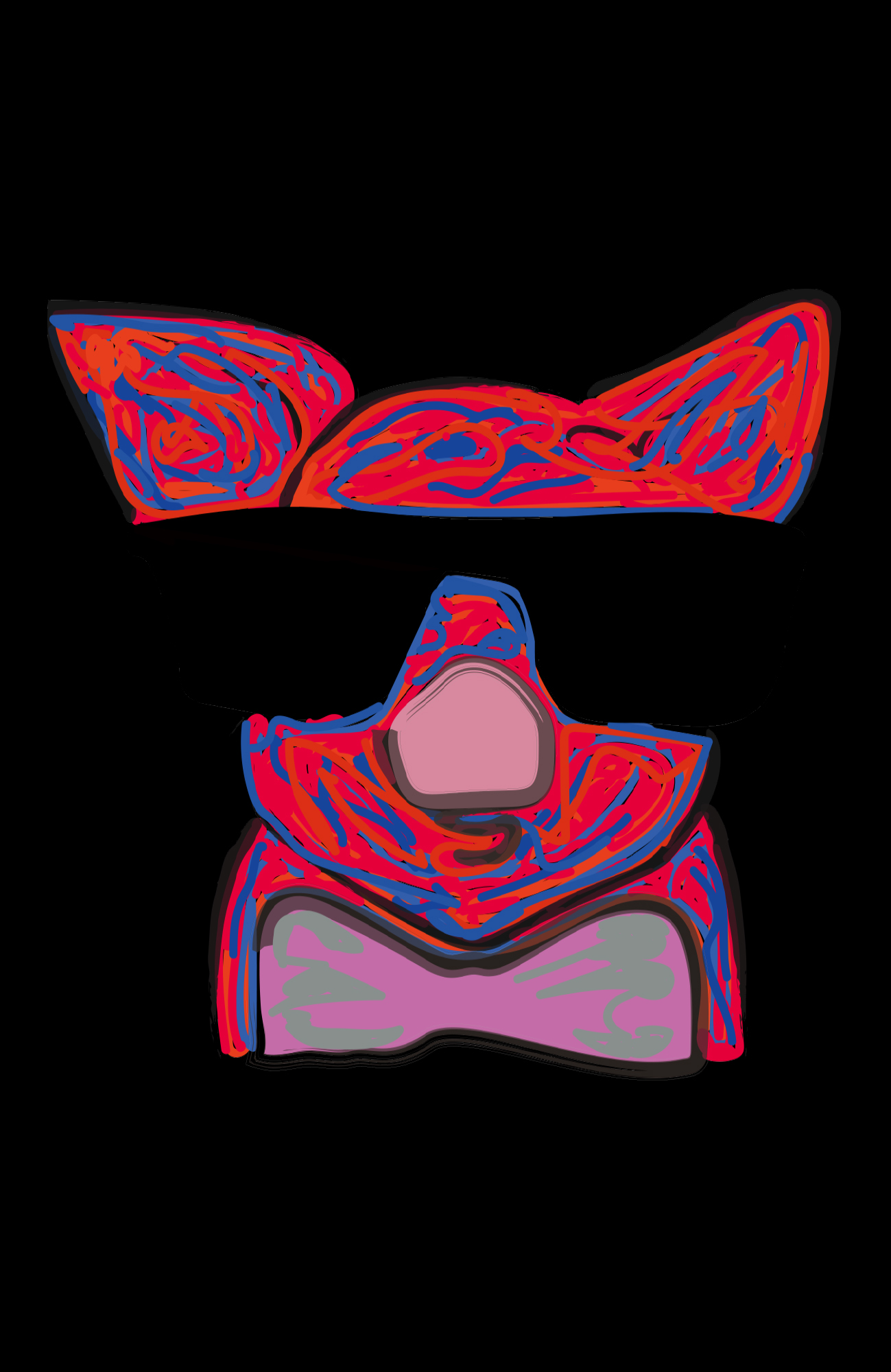その夏、私には友達と予定は合わなかったのだが、どうしても海に行きたいという日があった。
母に監視で『海について来てくれない』と尋ねると母からなんとかOK出たので、小学4年生の私は母と五島列島は蛤浜という塩の満ち引き次第では100メートル岸までの差が出るという浜に遊びに繰り出した。
もちろんのことではあるが、蛤浜に着くと同級生や知り合いの小学生が何人も遊んでおりそこで楽しみ始めたのだった。
私は、腕立て伏せのような状態で海に浸かりゴーグルをはめて海の中を手で歩き回るということが好きで1人でその遊びを続けていた。
遊んでいると、熱い日差しの中時間はあっという間に1時間、2時間と過ぎて行くのだった。それから私はふと海に浮かんでいる筏を目掛けて泳いでみようと思いたち、筏に向かって海底を蹴りながら前に進んでいた。
そんな折、筏までの途中で同級生のMikaに出会った。彼女もその大きな長身の身体で波をかき分けて筏に向かって歩いているところだった。
2人して筏に向けて海底を歩いているとMikaが急に私に向かって言ってきた『波が来るばい!』沖を見ると普段、五島列島を行き来しているフェリーが蛤浜の沖合を長崎市に向けて出港したところだった。
数分後に、フェリーからの余波の波がやってきて私たちは海底を歩くことが困難になってきた。波はどんどん高さを増し、私はその内、顔が波の上を出ないことが多めになってきて苦しくなってきた。ふと隣にいたはずのMikaが気になったが、Mikaは小学生の中でも長身なため、なんとか顔を海上に突き出しながら歩き海の上に浮いている筏に向かっていた。
その後、私は海の上に顔が出なくなり藁をもすがる思いで、もがき始めることになる。そんな折、目の前に大きな波が押し寄せてきて私は波に飲み込まれてしまった。一瞬にして、波に飲まれた私はパニックを起こしながら『これは、やばいぞ!』と子供心ながらに思った。
一瞬、顔が海面に出た瞬間に周りの状況を確認すると次の波もやって来ている。『やばい、やばい』という胸騒ぎと確信だけだった。なんとか、一旦は足が海底につき体勢を立て直した私に更なる波がやって来て、私はまた海底に引き摺り込まれた。
そして、長い海底の時間が過ぎた後、私の少し前をMikaが筏に向けて波立つ海面を横切っているのが見えた。私は死に物狂いでMikaに『助けて!』と声をかけた。が、しかしMikaもこの波の中で必死である。『あとでね!』と言った。
Mikaが筏の方に行こうとした瞬間に私はMikaの背中に必にしがみつき、半ばおんぶされるような形で筏まで歩くMikaにおぶられて命辛辛辿り着くことができた。
筏にたどり着きお互い必死だった顔を思い出して、ぷっと吹き出した2人は腹を抱えて笑い転げていた。
波が鎮まると、Mikaは身長がある為また海をてんてんと歩いて岸の方まで歩いて行ったが、何せ泳げない私は、さてどうしたものか考えて、いかだに掴まりながら足で海底までの深さを測ってみた。約水深2メートル。小学生の私にはなかなかの深さである。
小学生の私は先の恥ずかしさと怖さの為か、どうするかに考えがなかなか及ばなかったのだが、筏の上から一緒に海の監視に来た母を声の限り呼んでみた。しかし、母は母親仲間との話に夢中になって全く聴こえていないどころか、こちらを見る様子もない。
このままだと潮もまた満ちて来そうなので、仕方なくクロールで行けるところまで息継ぎなしで泳いで行って、そこで足がつかなかったら、また、その時考えようという大胆な作戦を思いついた。
とにかく、ガーっとクロールを小学生最大の力で泳ぎ続けた。どこまで進んだかは定かではないが、とにかく必死にクロールで息が続く範囲まで泳ぎ続けた。息が続かなくなった頃に、そーっと足を海底を探りながら下ろしていく。海底が…そこにはあった。『良かった…』安堵と安心のため息が漏れて私は程なく蛤浜の海から帰ることができたのだが、この夏の急死に一生の思い出を私は忘れない。そして、私の命を助けてくれたMikaのことを私は忘れない。